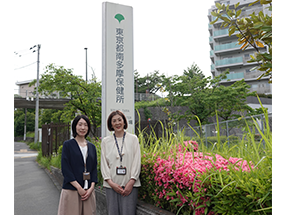南多摩保健所では、普段はどのような仕事をされていますか。
角田:私は、南多摩保健所の保健医療担当保健師として働いています。主な仕事は、医療安全支援センター「患者の声相談窓口」での相談業務や、管内の医療機関に向けた医療安全の確保に関する情報発信です。
能登半島地震の災害現場に派遣された経緯や、派遣が決まったときの気持ちを教えてください。
岡田:東京都は、災害があったときに被災地へ支援に行ける可能性がある職員を名簿登録しており、災害が起こったら、その名簿をもとに派遣する職員を調整して決定します。角田さんと私は名簿に登録をしていたため、今回の被災地派遣となりました。
角田:能登半島地震のニュースを見たとき、「私にも声がかかるかもしれない」とは考えていました。ただ、私には小さな子どもがいるため、「果たして被災地に行けるのかな」という悩みがありました。そこで、家族に被災地派遣の可能性があることを話すと、家族は「家庭のことはどうにかするから、被災地に行ってきて」と言ってくれました。そのため、実際に派遣の声がかかったときは、派遣を引き受けることに迷いはありませんでした。
保育園児の子どもにも、私が被災地支援に行くことを伝えました。「お母さんは困っている人を助けるんだから、アンパンマンになれるね」と子どもに言われたことで、「頑張らなくちゃ」と思えました。
被災地への派遣期間や業務内容について教えてください。
角田:私は、2024年1月19~24日までの5泊6日で、石川県金沢市内の「いしかわ総合スポーツセンター」に派遣されました。そこは1.5次避難所の位置づけでした。私は、保健師5名と業務調整員1名で構成された保健師班の「第3班」として被災地に行きました。
岡田:1.5次避難所は、能登半島地震で新たに開設されました。被災者は旅館やホテルなどの2次避難所に行きますが、高齢者や小さいお子さま連れの方など、すぐに2次避難所に行けない方たちが、1.5次避難所に滞在します。
角田: 避難所での主な業務は、被災者の健康管理や避難所の衛生管理でした。特に、感染症が流行していた時期なので、感染症対策の業務が多くなっていました。
また、1.5次避難所から2次避難所に移動する被災者の調整を行っていました。
避難所の支援で、大変だったことや困ったことはありましたか。
角田:避難所は、人手や物資が不足していたと思います。たとえば、慢性疾患がある多くの高齢者が、避難所に大量の残薬をもってきていました。どれが大事な薬かの判断が保健師だけでは難しく、服薬確認の人手やお薬カレンダーも足りない状況でした。
そのため、医師や薬剤師の方と連携して、大事な薬を優先的に飲んでもらったり、手作りのお薬カレンダーを使ったりして工夫しました。
また、避難所となった体育館内では手を洗う場所が足りず、発熱や感染性胃腸炎などの感染症が出続けていました。体育館内は家族ごとにテントが設置され、個室の状態になってはいますが、さまざまな「もの」や「人」を媒介して、感染症が拡がります。注意喚起や消毒はしていましたが、対応には苦慮しました。
多職種連携や支援チーム(DMAT・DWATなど)との連携はありましたか。
角田:DMATの医師に、避難所内の感染症対策で何を優先すべきかの相談に乗ってもらい、チームで連携する大切さを学びました。また、DWATやJRATの福祉職やリハビリスタッフとともに、福祉用具やリハビリが必要な被災者のアセスメントをし、避難所の安全管理にあたりました。
普段だと、職種ごとの役割分担を先に考えてしまいがちですが、避難所では職種に関わらず、「少しでも早く被災者の力になりたい」と、同じ方向を目指して動けたと思います。
角田:支援期間中、保健師は金沢市内のホテルに滞在していたため、ありがたいことに衣食住は整っている環境でした。
ただ、避難所内のリーダー業務を担当する日等忙しいときは、食事を摂る時間もなく一日中働き通しでした。避難所にいる間は、常に神経を張っている状態で、ようやくホテルに帰ってきても目が冴えてしまい、なかなか眠れないなどの苦労はありました。
非日常といえる環境で、癒されたことがあれば教えてください。
角田:一緒に派遣された班のチームワークがよく、冗談を言い合ったり、笑い合ったりできたのはよかったですね。仲間に話すことで、つらい思いを溜め込まずに済む状況が、私にとっては心の支えでした。
いつでも被災地に派遣できるように。保健所の業務体制を整備
後方支援の立場として、保健所で取り組んだことを教えてください。
岡田:私は角田さんより先に、保健師班の「第1班」として、いしかわ総合スポーツセンターでの被災者支援を行っていました。そのため、角田さんが避難所での活動をイメージできるように、私が現場で得た経験を伝えるようにしました。具体的には、東京都と石川県では気候が違うため、服装や荷物のアドバイスや1.5次避難所での活動状況などを伝えました。
角田さんが参加した「第3班」は発災から間もないこともあり、派遣の出発日が二転三転する状況でした。直属の上司である課長代理が中心となり、角田さんの業務内容を常に把握するようにし、いつ派遣されてもよいように引継ぎ体制を整えました。
災害看護に興味がある看護職へのメッセージをお願いします。
角田:私は、能登半島地震の被災地支援に行かせてもらって、本当によかったと感じています。被災地に行くまでは、不安な気持ちを抱えながら現場に入る人が多いと思います。ただ、被災地に行くと、自分ひとりで支援するわけではありません。「被災者の力になりたい」という思いで全国から集まった保健師や多職種の人たちと支え合いながら、避難所支援にあたれます。
もし、被災地支援の機会があって職場と家庭の環境が許すのであれば、ぜひ行ってみてほしいですね。
災害看護を経験した保健師として、今後の抱負を教えてください。
岡田:災害支援中は常に緊張状態で、活動内容も「これをやったらよい」という決まりが定まっているわけではありません。支援のフェーズがどんどん変わっていくため、柔軟な動きが求められます。角田さんは、被災地支援の体験を、ぜひ日常の業務に活かしてもらえたらと思います。
また、東京で災害が起きたときに備えて、「助けてもらう側」として、避難所避難者や自宅避難者への支援、他自治体からの応援などの対策も考えていきたいです。
角田:避難所支援を終えて、「被災者にもっと何かできたのでは」という不全感が残りました。避難所の業務に追われて、被災者の苦労や家族を亡くしてつらい気持ちを、十分に聞けない葛藤があったのです。この葛藤をよい形で活かせるように、地域で困っている方の支援をしていきたいです。
被災地支援をとおして、日々の地区活動が災害時の保健活動でも生きることや、保健師の力を感じました。災害支援は、母子保健や精神保健などの幅広い視点が必要なので、求められたときはまた被災地に行けるように経験を積みたいと思います。
私は、被災して大切な人や住む家をなくしながらも、懸命に生きようとする住民の姿に心を動かされました。これからも保健師として多くの人の支えになりたいと思っています。